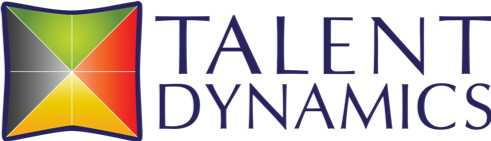●組織が停滞する“見えない共通点”
業績が向上しない組織には、
ある共通した“構造”が存在します。
それは、成果が問われず、
やるべきことをやらなくても
誰にも責められない状態です。
本人も周囲も問題意識を持たないまま、
時間だけが流れていく──。
そんな“甘えの構造”に、
思い当たることはないでしょうか?
—
ロードプロファイル
喜多庸元(きた のぶゆき)です。
IT企業経営とICT顧問をしています。
●なぜ「文化」より「構造」なのか?
私はこれまで、
組織変革や経営支援の現場で
数多くの企業を見てきました。
そこで気づいたのは、
「文化をつくる前に、
成果が出る構造を整えていない」
企業ほど、
変化が遅いということです。
とくに、経営層が
理念や価値観の浸透を唱えながら、
現実には数字から目をそらしている。
そんなケースも少なくありません。
●理念が“免罪符”になるとき
理念経営とは、本来、
組織の方向性を一致させ、
自律的なチームを育てる力強い仕組みです。
しかし、
構造が整わないまま導入されると、
逆に“逃げ道”になってしまいます。
「理念を作れば大丈夫」とか、
「うちの会社には立派な理念がある」と、
自社に酔ってしまってはいないでしょうか?
努力の方向性も成果も曖昧なまま、
「うちは人を大切にしている」
と言うだけでは、
現場は動きません。
●経営理念はいつ作るべきか?
多くの経営者がやりがちなのが、
成果の出ていない段階で
経営理念を定めようとすることです。
しかし、それでは
成果を挙げられない社員が定着する
土壌をつくってしまいます。
本来、経営理念づくりは
成果が挙げられる構造を作ってから
取り組むべきものです。
そうすることで、
“成果を出す社員が居心地よく働ける組織”
が生まれ、理念が“結果の背景”として
定着していくのです。
●なぜ甘えの構造が生まれるのか?3つの要因
この“構造的甘え”がなぜ生まれるのか。
原因は主に以下の3つに集約されます。
– 役割と成果が明確に結びついていない
– 評価の基準が曖昧、もしくは存在しない
– 経営層が数値管理や厳しい対話から逃げている
理念や文化で包み込むことで、
これらの構造上の欠陥が隠れてしまうのです。
●成果を前提とした設計が文化を活かす
これを打破するには、まず
成果を前提とした組織設計が必要です。
とくに重要なのは、以下の3点です。
– 才能と役割の適合
– 成果に対する期待の明示
– 成果に基づく透明な評価
これらが整ってはじめて、
理念や文化は機能します。
逆に、これらが欠けたままでは、
理念はただのポスターでしかありません。
●エンゲージメントは成果構造の上に成立する
「エンゲージメントを高めたい」
と考える経営者や人事は多いでしょう。
しかし、成果の設計と
責任があいまいな状態では、
どれだけ心理的安全性や理念を
強調しても効果は限定的です。
貢献と成果の手応えがあるからこそ、
信頼も生まれ、文化が“実感”として
浸透していくのです。
・・・
数字から逃げる経営は、
文化を育てるどころか、組織を弱くします。
逆に、成果を前提とした
“構造”を整える経営こそが、
本当に人を活かし、理念を実現する
土台となるのです。
(一社)日本適性力学協会
認定WDコンサルタント
喜多庸元
<お知らせ>
来年2月に開催の
『ウェルス経営デザインキャンプ』
https://jwda.mykajabi.com/wealthdesigncamp
あなたのビジネスパートナーや
幹部たちと一緒に参加しませんか?
個性が役割になる:
誰が“何をしないか”まで明確に
役割と数字が噛み合う:
誰がどの数字(KPI)を伸ばすかが明確になる
人が自然に動く:
合意→割り当て→翌日から運用の“流れ”を実装
メッセージと行動が一本化:
社内外の発信と現場の動きが揃う
など、合宿明けから
すぐに現場で使える解決策を
お持ち帰りいただけます。
※無料の事前相談も受け付けています。
※研修費として計上できるよう
領収証や必要書類の対応もさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
↓↓↓
−−−−−−−−−−
ウェルス経営デザインキャンプの詳細はこちらから
https://jwda.mykajabi.com/wealthdesigncamp
−−−−−−−−−−
最新記事をメールで受け取れます。
ご購読登録はこちらから
https://jwda.org/newsletter_entry_sainoukeieitd/