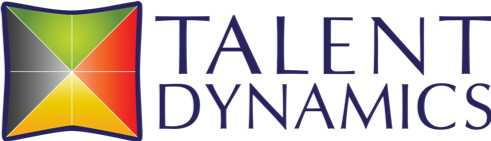なぜ今、『人材育成』から
『才能開発』への転換が
求められているのでしょうか?
その背景には、
企業の競争優位性を支える
人材戦略の変化があります。
かつてはスキルの習得が重視されていましたが、
今では『個の才能を活かす』ことが求められています。
今回は、その理由と
実践方法を徹底解説するとともに、
導入時によく直面する課題や
解決策にも触れていきます。
・・・
ロードプロファイル
喜多庸元(きた のぶゆき)です。
IT企業経営とICT顧問をしています。
●人材育成と才能開発の違い
これまでの人材育成は、
社員が業務を遂行する上で必要なスキルを
向上させることを目的としてきました。
教育プログラムや研修を通じて、
標準化されたスキルや知識を
社員に習得させるアプローチは、
特定の業務プロセスにおいて
一定の効果を上げてきたと言えるでしょう。
しかし、テクノロジーの進化が進む現代では、
業務の多くが自動化やデジタル化され、
標準的なスキルの重要性が相対的に低下しています。
それに伴い、予期しない状況や
急速な変化に柔軟に対応できる力が、
これまで以上に求められる時代となりました。
こうした時代の要請に応えるのが
「才能開発」というアプローチです。
才能開発は、個々の社員が持つ
「潜在的な才能」を発見し、それを
最大限に活かすことを目指します。
才能とは、たとえば分析力や調整力、
アイデア創出力といった、人それぞれが持つ
独自の強みを指します。
これらの才能は、
業務に直接的な貢献をするだけでなく、
組織全体の創造性や効率性を高める上で、
極めて重要な要素となるのです。
●才能を『活かす』ための3つの重要な視点
見抜く力:
社員の才能を見つけるための
『観察力』と『評価力』が求められます。
活かす力:
才能を活かすための『環境設計』と
『役割の明確化』が不可欠です。
支える力:
フィードバックや心理的安全性の確保が、
才能を最大限に活かすための支えとなります。
●才能を活かすための具体的なアクションプラン
才能を活かすためには、
・才能の見える化
・適材適所の人事配置
・業務設計の見直し
の3つのアクションが重要です。
まずは「才能の見える化」を行うことです。
社員一人ひとりの才能や
得意分野を明確にするために、
社員のプロファイルを作成します。
適性を可視化する際には、
主観性バイアスを避けることが重要と考えがちですが、
それ以上に本人が納得感を持つことが大切です。
正確さにこだわりすぎるのではなく、
大まかなプロファイリングからスタートし、
まずは進めることを優先する
アプローチが効果的です。
その後、周囲からの評価や本人の
納得度を検証する仕組みを取り入れることで、
プロファイリングの実効性を高めることができます。
こうした柔軟な進め方が、
才能の見える化を円滑に進める鍵となるでしょう。
そのためにも
「お試し配置」期間を設けることが有効です。
この期間中に本人やチームメンバーの
フィードバックを収集し、本配置を
調整する仕組みを作ります。
また、異動や配置転換に伴う
コミュニケーションコストを減らすために、
事前に期待役割や目標を共有し、
定期的な面談で進捗確認を行うことが効果的です。
「才能に適した業務プロセス」を設計するには、
まず明確に期待する成果や方針を示し、
業務プロセスの再設計を社員の裁量に
委ねることが重要です。
例えば、創造的な仕事が得意な社員には、
ゴールと期限を明示しつつ、プロセスは
自由に構築させることで試行錯誤を促します。
一方、分析力が必要な業務では、
成果基準を示した上で進め方を
工夫させると精度が向上します。
指示と裁量のバランスを取ることで、
組織の負荷を抑えながら才能を活かせます。
●才能開発のチェックリスト
以下の7つのポイントで、
貴社の才能開発の進捗を確認しましょう。
1. 社員の才能が大まかにプロファイリングされているか?
完璧さにこだわりすぎず、
まず大まかな才能の見える化が
進められているかを確認します。
2. 本人がプロファイリングに納得しているか?
周囲の評価だけでなく、
社員自身が結果に納得しているかを
確認する仕組みがあるか。
3. 「お試し配置」を活用し、適材適所の試行が行われているか?
本配置の前に試行期間を設け、
フィードバックを収集しているか。
4. 異動や配置転換時に期待する役割と目標が共有されているか?
配置時に必要なコミュニケーションが
適切に行われているか確認します。
5. 業務設計において社員の裁量が確保されているか?
明確な目標を示した上で、
業務プロセスの再設計を社員自身に委ねているか。
6. 才能開発に関する定期的なフィードバックの場が設けられているか?
本人やチームメンバーからの意見を取り入れる仕組みがあるか。
7. 才能活用が組織全体の成果や効率性向上につながっているか?
才能開発の取り組みが具体的な成果に
結びついているかを検証するプロセスがあるか。
●まとめ
『才能は育てるものではなく、引き出すもの』。
この考え方こそが、才能開発の本質です。
一人ひとりの個性や強みを活かすことで、
組織全体のパフォーマンスが向上します。
才能を引き出すためには、
・具体的な才能モデルの設定
・主観バイアスの排除
・失敗パターンへの対策
が重要です。
まずは、才能を見える化することから
始めてみてはいかがでしょうか?
才能プロファイリングはこちらから
https://talentdynamics.jp/td_test/
(一社)日本適性力学協会
認定WDコンサルタント
喜多庸元
最新記事をメールで受け取れます。
ご購読登録はこちらから
https://pardot.profiletest.net/l/1001531/2024-02-08/wzxk